代表部の活動 : 神野耕輔 二等書記官
令和3年3月9日
ASEANの競争法・政策と我が国の貢献二等書記官 神野耕輔 (2018年6月~公正取引委員会より出向) |
|
1 はじめに私は、2018年6月から、公正取引委員会から外務省に出向し、ASEAN日本政府代表部(在インドネシア大使館兼任)で競争法・政策を担当しています。今回、ASEANにおける競争法・政策に関する取組や、我が国の関わりについて簡単に紹介させていただきます。競争政策は、事業者の公正かつ自由な競争を促進し、事業者が自主的な判断で自由に活動できるようにすることによって、経済を活性化し、豊かな社会を実現していくことを目指した政策です。そして、競争法は、カルテル、談合、新規参入阻害行為などの競争を阻害する行為の禁止等を定めた法律であり、市場メカニズムを有効に機能させるための基本的ルールといえます。我が国では、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)が競争法に該当し、公正取引委員会が競争当局として独占禁止法の運用を担っています。 歴史を振り返ると、19世紀後半にカナダや米国で競争法が導入され、我が国では第二次世界大戦後の1947年7月に独占禁止法が施行されましたが、世界的に競争法の導入が進んだのは、東欧諸国が市場経済に移行した1990年代以降です。こうした流れの中で、ASEAN各国では1990年代後半のアジア通貨危機を1つの契機として競争法の導入や競争当局の設立が進みました(2021年2月現在、9カ国で既に施行済み、残る1カ国でも施行に向けた手続が進められているところです)。 一方で、ASEAN各国においては、事業者・市民の競争法・政策に関する認知度の向上や、各競争当局の組織・能力の強化などの課題がまだまだ山積しています。また、ASEAN各国の競争当局の間でも、設立から20年を超えて法執行経験を蓄積しつつある当局がある一方で、設立後まもなく規模も小さく経験も乏しい当局もあり、格差が存在するのが現状です。 2 ASEANにおける取組ASEANでは、2015年11月にASEAN経済共同体(AEC)が設立され、域内の経済統合の深化に向けた取組が進められています。事業者の活動範囲が拡大することで顧客・消費者にとっての選択肢も拡大し、競争の活発化による経済の活性が期待されますが、その一方で、新規参入排除などの反競争的行為によって、こうした経済統合の果実が損なわれてしまうおそれもあります。そのため、各国の競争当局がそれぞれ反競争的行為に適切に対処するとともに、各当局が協力することの重要性が一層増すことになります。ASEANでは、AECの設立に合わせ、経済統合の工程表である「AECブループリント2025」が策定され、その5本柱の1つとして、「競争力のある、革新的、ダイナミックなASEAN」が掲げられています。そこでは、競争政策に関し、競争力のある、革新的な地域の形成をサポートし、自由化及び生産拠点・市場の統合を促進するための重要な手段として、効果的な競争ルールが必要であるとされています。その上で、戦略的な手段として、(1)効果的な競争法制を確立すること、(2)競争関連当局の能力を強化すること、(3)競争への認知を促進すること、(4)競争法・政策に関する地域協力協定を策定すること、(5)ASEANにおける競争法・政策の一層の調和を達成することなどが掲げられています。 実務の上では、上記のブループリントを更に具体化し、達成目標時期を明記したアクションプランが策定されており、ASEAN各国の競争当局から構成されるASEAN競争専門家会合(AEGC)が、その進捗管理を行っています。AEGCは年2回、各当局の持ち回りで開催され、アクションプランの進捗管理のほかにも、例えば、2020年6月には、新型コロナウイルス感染症流行下における競争法執行に関する声明を発表するなど、ASEANの各競争当局が連携して取り組むべき、その時々の課題への対応が議論されています。また、AEGCでは、日本、オーストラリア等との対話会合も開催されており、各国との具体的な協力状況に関する報告や、今後の協力の方向性に関する意見交換などが行われています。こうした会合には、日本から公正取引委員会の担当者が参加しているほか、ジャカルタのASEAN代表部からも参加しており、私自身も2019年のマレーシア・ランカウイ会合等に参加し、日本とASEANの競争政策担当者間の議論に関与するとともに、交流を深める機会を得ました(写真)。  3 ASEAN競争当局の能力強化への支援ASEAN各国の競争当局は、前述のとおり、法執行に係る能力・経験の不足等の課題を抱えています。また、今後ASEANの経済統合が深化するにつれ、競争当局が互いに協力することが必要となる事例が増加することも予想されますが、そのための体制の構築や強化も必要です(ASEANには、我が国を始めASEAN域外からも多くの事業者が進出・活動しており、今後、域内のみならず、域外の競争当局との協力の必要性が高まることとも想定されます。)。こうした諸課題に対応、つまり、ブループリントを実行するための取組の1つとして、インドネシアの競争当局である事業競争監視委員会が提案者となり、日ASEAN統合基金(JAIF)を活用したプロジェクト「ASEAN地域における競争法執行強化のためのASEAN競争当局に対する技術支援」が実施されています。このプロジェクトの下では、競争法の専門家として我が国の公正取引委員会職員や競争法研究者等を講師とするセミナー等が開催されるほか、ASEAN各国における競争法・政策に関する認知度の実態調査、国境を跨ぐ事件の共同調査に係る手続の研究など、様々な活動が行われています。 我が国は、これまでも、長年にわたる独占禁止法運用の経験を活かし、競争法・政策に関し、ASEAN各国に対し個別に支援を行ってきました。各国の置かれた状況やニーズを踏まえた支援は引き続き重要ですが、それと同時に、経済統合を深めるASEANに対して横串を通した支援を実施していくことの重要性が高まっていると考えられます。 4 おわりに「ASEANにおける競争法・政策の一層の調和を達成すること」とブループリントに掲げられているとおり、ASEANでは、先んじて地域経済統合を実現した欧州連合(EU)でいわゆるEU競争法が運用されているように地域共通の競争ルールを導入するのではなく、各国の競争法・政策の調和を図っていくというアプローチが取られています。ASEANが各国の競争法・政策をどのように一体感を持って発展させていくのか今後が注目されるとともに、ASEANにおける競争法・政策の発展に対し、70年以上の競争法執行に係る経験を持ち、ASEANとの経済的な結びつきも強い我が国が、どのような貢献を行うことができるのか、ASEAN側からの期待の高さを日々の業務の中で感じているところです。以上 |
|
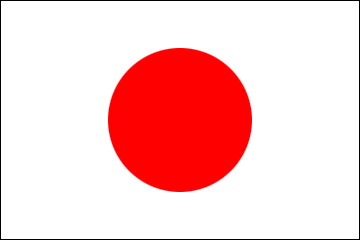 ASEAN日本政府代表部
ASEAN日本政府代表部 