代表部員の活動 : 参事官 伊藤 淳
令和7年9月24日
精密司法から「ティダアパアパ」の世界に入ってみて参事官 伊藤 淳 (2022年~ 法務省から出向) ※以下の内容は、ASEAN日本政府代表部の立場や意見を代表するものではなく、あくまで私自身の個人的見解です。 |
 オンライン詐欺対策センター設立に向けて 一緒に仕事をしたASEANAPOLE事務局にて |
1 はじめに私は、検察官であり、主に、日本国内で発生する刑事事件の捜査・公判を担当していました。日本の刑事司法制度は、「有罪率99%」などとの言葉とともに「精密司法」とも呼ばれていました。外国人が被疑者、被告人、被害者になった場合でも、日本語を使って(裁判所法74条)、日本の刑事訴訟法の厳格な手続きの下で、捜査・公判を進める仕事をしていました。その私が、2022年8月から2025年9月まで約3年間、ASEAN日本政府代表部の一員として、「法務・司法」、「越境犯罪」、「人権」分野における日本とASEANの協力に関する活動をしました。 ASEANは、国境を越えて、国土・人口規模、経済規模・経済発展水準、政治体制、宗教、社会文化が異なる東南アジアの国々が協力するための地域的な枠組です。言葉を選ばず言えば、ある種「カオス」的なところがあります。3年間仕事をした実感として、よくこれだけバラバラの国が集まって協力しようなどと考えたものだなと感心します(実際のところ、ASEAN各国それぞれの考えと、ASEAN加盟国としての発言が異なることもよくあります。)。そこにはお互いに違いを認めて許容し合う文化が存在するのだと理解しましたが、許容するラインを理解できず(私自身が許容できず)困ったこともありました。とはいえ元々の職業の影響でどちらかと言えばきっちりした(しすぎた)ことを好む私が3年間大過なく過ごせたのは、ASEAN各国の皆様の大らかな精神(インドネシアでは「ティダアパアパ」と言ったりします。私が昔仕事をしていたラオスでは「ボーペンニャン」などと言います。「気にしない、気にしない」という意味です。)で私を許容してくれたおかげでもあります。最後に、検察官だった私が、ASEAN相手に、どのような業務をしていたか、皆様に紹介したいと思います。 2 法務アタッシェの仕事(ASEAN法務・司法、越境犯罪、人権分野協力)(1)法務省・検察庁が主管する法務・司法分野の業務は国内的なものが大半です。しかしながら、法務省は、30年近く、JICAともに、ASEAN諸国等に対して法制度の整備を手助ける事業を行ってきました。文化や言語の違う国でのこれらの事業は時間がかかるものですが、日本はASEAN側の事情に配慮しつつ事業を進めてきたため、法務・司法分野における日本に対するASEANの信頼は他国の追随を許さないぐらい高いものでした。日本は、この信頼を土台に、ASEANとの友好関係を進化させるために、2023年の日ASEAN友好協力50周年を一つのきっかけにして、これまでバイの関係が中心だったASEANとの協力関係をマルチの関係に広げました。具体的には、日本法務省はASEAN法務分野との関係で2021年に初めての対話国となり、2023年には、東京で、ASEAN各国の法務大臣等(に加えて、同年は日本がG7議長国だったこともありG7の法務大臣等)による日ASEAN特別法務大臣会合(及びASEAN―G7法務大臣特別対話)を開催し、法務・司法分野における様々な内容の日ASEAN協力について定めた日ASEAN法務・司法ワークプランを採択しました。そして、法務省は、2023年以降も、ASEANとの間で、日ASEAN法務・司法ワークプランに基づく刑事・民事等の様々な活動を実施してASEANとの友好関係を強化していき、2025年には、常設の日ASEAN法務大臣会合を設立するに至りました(同年11月マニラにて第1回が開催されます。)。同会合は、ASEAN法務・司法分野では初の域外国との常設の閣僚級会合(ASEAN+1閣僚級会合などと言います)で、かつ、日ASEAN友好協力50周年後では第一号の閣僚級会合設立となりました。私は、法務アタッシェとして、日ASEAN特別法務大臣会合・ASEAN-G7法務大臣特別対話開催のためのASEAN側との交渉・調整、日ASEAN法務司法ワークプラン採択に向けたASEAN側との文言交渉、さらには、同ワークプランの実行のための各種プロジェクト実現に向けた各種調整、日ASEAN法務大臣会合設立・常設化のためのASEAN側への働きかけ等を、法務省と協力して担当しました。全てが初めての仕事であり前例がなく、ASEANと日本の仕事の進め方の違いなどから大変なこともそれなりにありましたが、法務・司法分野における日ASEAN関係が着実にかつ目に見える形で進歩・強化されていくのを感じながら業務を担当できたのはやりがいもあり、幸せでした。この過程で築いたASEAN側のカウンターパートとの関係は一生ものだと感じております。今後後のキャリアにおいて、お互いに立場を変えた上で再会し、また一緒に仕事をすることを大変楽しみにしています。(2)私は、法務アタッシェでしたが、検察官出身で刑事分野が専門ということもあり、(主として警察庁が担当する)越境犯罪分野の業務も担当させていただきました。同分野は伝統があり、私が着任した2022年には既に、日ASEAN関係だけでなくASEAN+3(日本、中国、韓国)の協力枠組みもあり、日ASEAN及びASEAN+3で協力して実施すべき活動計画も存在しました。そのため、同分野での私の業務は、法務・司法分野と異なり、協力枠組みを新たに立ち上げるのではなく、既に存在する協力枠組み・活動計画を着実に遂行することでした。しかし、ここでも色々と問題がありました。ASEANは、中心性・一体性という行動原則を持っています。これはASEANが、対外関係について、ASEANを中心に据えて考えること、ASEANを個々ではなく一体として扱うように、日本を含むASEAN域外国に求めるものです。これはそうしないと、多様性を有しながらも地域統合を目指すASEAN加盟国が、域外国との関係でバラバラになってしまうことを防ぐためのASEANの知恵で、日本もこの原則を支持しています。越境犯罪分野は、かつて(コロナ禍以前)、テロ・サイバー犯罪・人身取引等の様々な日ASEAN協力プロジェクトを実施するなど活発に活動をしていました。しかしながら、コロナ禍に続き2021年のミャンマークーデターにより状況が一変しました。従来どおりのミャンマー当局との協力が難しくなったのです。日本政府としては、ミャンマーにおいて状況改善の兆しが見られない状況が継続していることを深刻に懸念しており、ミャンマー支援の在り方については、支援を必要とするミャンマーの人々に直接裨益する人道支援を積極的に実施していく方針です。他方この場合、ミャンマーと他のASEAN加盟国を一体のものとして扱うことを求めるASEAN一体性とは、具体的な協力案件の実施にあたっては齟齬が生じることがあります。結果、越境犯罪分野では日ASEAN協力事業を遂行することは、従来通りのやり方では難しくなりました。このような状況のため、私は、越境犯罪分野では、ASEAN越境犯罪分野の動向(ASEAN側の考えや他の同志国等の動き)を調査するなどして、来るべき時に新たな日ASEAN協力事業を形成できるよう準備することしかできませんでした。このまま任期が終わるのかなと諦めかけていたところ、任期も残り半年程度になった2025年2月頃、いわゆるオンライン詐欺対策がASEANや日本を含む域外国(米国、豪州、中国、韓国等)で大きな問題となりました。特に、日本の高校生らがミャンマー・タイの国境付近の施設に軟禁されて特殊詐欺に関わっていたことが大きく報道されると、日本国内でも喫緊の課題として大きな問題となりました。国際化・越境化が進むオンライン詐欺対策を効果的に実施するためには、ASEAN全ての国の関与が不可欠です。日本の対ミャンマー支援の基本的な方針に変わりはありませんが、ASEANが進めているオンライン詐欺対策の取り組みに日本政府が適切な方法で関与する形での日ASEAN協力の在り方が検討されています。私は、任期の最後の半年間、オンライン詐欺対策の取り組みに従事し、この取り組みに関する日ASEAN協力の在り方に一定の道筋を立てることができました。私は、この業務の過程で、ASEAN各国にオンライン詐欺対策を専門とするセンター(Anti-Scam Center、国家詐欺対策センター)が存在することを初めて知り、そのうちでも実績のあるタイ・マレーシア・シンガポールの詐欺対策センターを訪問して業務内容等について話を聞く機会を得ました。オンライン詐欺を始めとするサイバー犯罪の越境化は深刻で日本でも大きな問題になっています。私は、検察官に戻った後、おそらくオンライン詐欺を始めとする越境サイバー犯罪の事件(その中でも舞台がASEAN各国の事件)に従事する機会が必ずあると思います。日ASEANオンライン詐欺対策プロジェクト形成過程での経験は、私の今後の検察官人生にも必ずや生きるものと考えております。 (3)そして、私は、偶然の産物ですが、人権分野の業務も担当することができました。日ASEAN人権分野では、私の着任以前も、AICHR(ASEAN政府間人権委員会)との関係でいくつかの活動が存在しましたが、コロナ禍の影響等あり、私が着任した2022年9月時点では、ほぼ活動が停止していました。私が前任から引き継いだ業務にも人権分野の活動は含まれていませんでした。しかしながら、先述の日ASEAN特別法務大臣会合に関する業務の関係で、AICHRインドネシア代表と知り合うことになり、同代表を通じてASEAN人権分野の活動を認識するに至りました。その後、日ASEAN友好協力50周年といういわばお祭り的な雰囲気の中で、人権分野でも何か活動をすべきではないかとのモメンタムに乗って、かつて存在したAICHR代表らとASEAN代表部大使によるハイレベル対話(日AICHRインターフェース)を復活させ、同インターフェースで合意した「ビジネスと人権」をテーマにした活動を日ASEAN統合基金(JAIF)を使うなどして実施することができました。なお「ビジネスと人権」は2011年に採択された国連の指導原則を出発点とするものですが、貿易・経営や労働の問題にとどまらず気候変動やAI、越境犯罪などの問題とも関係し、各国が国別活動計画を策定するなど、官民一体となって様々な内容に取り組むべき面白いテーマになっています。今後も、日ASEAN人権分野で、「ビジネスと人権」を土台にして効果的かつ魅力的な活動が続けば良いなと願っています。法律家というバックグラウンドをもつ私にとって、「人権」は極めて身近でありつつも、取扱いが難しいテーマでもありました。偶然ではありましたが人権分野での活動に関わることになり、AICHR代表等のASEANにおける人権専門家と、時には専門的な内容(マニアックな内容)についても協議しながら、具体的な活動を作り上げた(再構築した)のは、今後の私の法律家人生にとって、非常に良い経験となりました。 3 大使館・代表部員としての仕事(大型ロジ)私は、法務アタッシェとしての上記の業務の他に、時に、インドネシアとの二国間関係を担う在インドネシア日本大使館と一緒に、大型行事の準備に加わることもありました。赴任中の3年間で、天皇皇后両陛下インドネシア御訪問、ASEAN関連首脳会議、日ASEAN友好協力50周年会議、石破総理インドネシア訪問含め、多くの大型行事を経験しました。大型行事では、総務班・行事班・配車班・プレス班などの業務ごとに細かい班に別れるのですが、各班には普段一緒に仕事をする機会が少ないインドネシア日本大使館員の方々も含め、業務を通じて色々な交流をすることができ人間関係を広げる良い機会になりました。天皇皇后両陛下インドネシア御訪問に際しては、日よけのない世界遺産ボロブドゥール遺跡に何度も登って、天皇陛下の御視察がスムーズに進むか、またメディアの方々が問題なく撮影を行えるか、確認しました。また、日本で行われた日ASEAN特別首脳会議に際しては、訪日したブルネイ代表団のケアを担当し、ブルネイ国王の入国が円滑に進むよう調整に携わるなど、検察官としては経験することは絶対にないと思われる業務に携わることができたのも、非常に良い思い出です。4 業務の合間に(ランニング、ゴルフ、サッカー、旅行)私は、幸いなことに、3年間、家族でインドネシアに赴任することができました。2人の子供はジャカルタ日本人学校(JJS)に通い、良い友達、先生に巡り合うことができました。また、家族全員そろってという機会はそれほど多くはなかったですが、それぞれがインドネシア・ASEAN各国を旅行することもできました。離任に当たり、家族に赴任生活を聞いてみたところ、大満足であり、「帰りたくない」などとも言っていました。この3年間は家族にとっても充実した時間だったのかなと感じることができたので、家族からこの言葉を聞けたのは、うれしかったですし、正直ほっとしました。また、私自身も、もともとの趣味のサッカーだけでなく、ランニング・トレイルラン・ゴルフと趣味を広げることができ、その過程で様々な仲間と貴重な体験ができました。私が勤務したASEAN代表部は、非常に仲が良く、趣味のランニングやトレイルランの関係で、インドネシア国立大学でのリレーマラソン大会、ブルーファイアが見えるイジェン湖へのトレイルラン旅行などを部員と一緒にでき、学生に戻って、部活の大会、修学旅行に参加しているような気分になり、とても良い思い出を作ることができました。 5 おわりにASEAN代表部での3年間は、様々な新しいことにチャレンジすることができ、公私ともに非常に充実した時間であり、思い残すことはありません。私は、この後、検察官の職に復帰し精密司法の世界に戻りますが、ここでの経験を活かして、ティダアパアパの精神を忘れずにおおらかな気持ちを持って、様々なことに取り組みたいと思っています。3年間ありがとうございました。 |
|
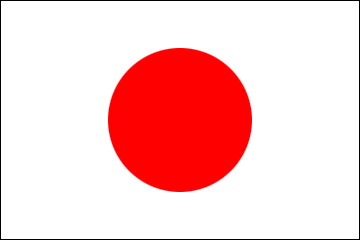 ASEAN日本政府代表部
ASEAN日本政府代表部 