代表部員の活動 : 井熊 伸吾 一等書記官
令和6年6月5日
ASEAN交通・観光・連結性と日本一等書記官 井熊 伸吾 (2021年~ 国土交通省より出向) ※以下の内容は、ASEAN日本政府代表部の立場や意見を代表するものではなく、あくまで私自身の個人的見解です。2021年9月末時点の状況を基に記載しています。 |
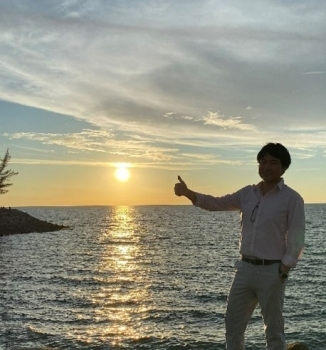 (ブルネイの夕日と筆者) |
1 はじめに2021年6月、国土交通省から出向し、ASEAN日本政府代表部にて勤務することとなった私は、COVID-19の影響が世界中に広がる中、インドネシア・ジャカルタに降り立ちました。東南アジアを訪れるのは学生時代以来10数年振り、かつ初めてのインドネシアという身からすると、高層ビルが並び立つジャカルタの発展振りに驚く一方、(パンデミックの影響緩和後は)街中にたくさんある屋台やバイクの路駐・逆走、不思議な道路交通による渋滞など、イメージしていた東南アジア感も色濃く残っているなと感じました。そんな私は、交通、観光及び連結性といった分野を当部で担当しており、どのような業務を行っているか、紹介したいと思います。 2 交通・観光交通及び観光分野は、それぞれ毎年開催される日ASEAN交通大臣会合及びASEAN+3観光大臣会合といった枠組みの下、様々な協力が行われています。交通分野においては、昨年の大臣会合の場において、日ASEANの今後10年間の新たな行動計画である「ルアンパバーン・アクションプラン」を採択するとともに、ASEAN事務局及び議長国ラオスの協力の下、日ASEAN友好協力50周年及び日ASEAN交通連携20周年を記念する特別セッションを開催しています。その中の具体的プロジェクトには、全世界衛星航法システム(GNSS)の導入計画に係る研修等、当代表部が担任するJAIF(日ASEAN統合基金)を活用して支援しているものも含まれており、会合でのプロジェクト採択に向け、ASEAN事務局等各関係者との調整を実施しています。 観光分野においてはASEAN+3の行動計画に基づく取組を実施しているほか、昨年の日ASEAN友好協力50周年を記念し、「日ASEAN観光大臣特別対話」を昨年10月に東京で開催しました。観光においてASEAN+日本の枠組みがない中、閣僚級を日本に招待してイベントを開催するには、日本側だけでなく、ASEAN事務局、議長国を始めとするASEANサイドの理解と協力が不可欠です。観光分野は、「日本からASEAN側」のみならず、双方向の交流拡大による「ASEAN側から日本への」経済・社会的影響も大きいことから(例えば、シンガポールのシンクタンク(ISEAS)がASEAN加盟国国民に実施した調査において、休暇の旅行先として、日本はASEAN諸国及び対話国の中で一番人気)、ASEANサイドの理解と協力を得、初の閣僚級特別対話を実現できたことは大きな意義があったと感じています。 3 連結性そもそも「連結性」、という言葉にあまりなじみがない方も多いのではないかと思います。ここでの連結性(Connectivity)は、鉄道や道路等の交通インフラで地域がつながり、移動しやすくなる、といった物理的連結性が最もわかりやすいですが、留学や観光といった人の移動・交流や各国の規制制度についても、人的・制度的連結性として、連結性の分野に含まれています。ASEANにおける連結性という言葉は比較的新しいもので、2009年のASEAN連結性に関するASEAN首脳宣言において、連結性の考えや重要性が確認され、これを踏まえ2010年にASEANの連結性マスタープランが策定されました。 現在は「ASEAN連結性マスタープラン2025」において、ASEAN連結性が地域の競争力、包括性、結合に寄与し、ASEAN共同体の政治安全保障・経済・社会文化の3つの柱を支えるものと位置づけられ、同計画に基づき様々な取組がなされています。同計画に基づく取組について議論する場として、ASEAN連結性調整委員会・対話国等協議が毎年開催され、日本からも参加しています。 日本も多くの連結性支援を行っており、昨年9月の日ASEAN首脳会議及びASEANインド太平洋フォーラムでは、岸田首相から、日本とASEAN諸国において様々な連結性協力進めていく「日ASEAN包括的連結性イニシアティブ」が発表されました。 4 おわりに私の担当分野で様々な協力が行われていますが、ジャカルタに在住し、各種ASEAN支援をする中で感じるのは、日本の知見・技術がまだまだ求められる分野がある一方、日本も学ぶべき分野があるということです。例えば、基本的なインフラ、計画やルールの整備は追いついていない中、キャッシュレス決済や配車アプリといったオンラインサービス等は非常に進んでおり、リープ・フロッグが生じています。このような社会経済の動きは、功罪併せ持ちつつも、その変化や変化への適応速度、柔軟性等、見習うべき点も多いと感じます。近い将来、ASEANの経済規模が日本を追い抜くと予想され、かつシンガポールといった先進的な国も含まれる中、今後、日本がASEAN諸国から何を学び、得られるかという観点も持ちつつ、日ASEAN関係に携わっていきたいと考えています。 |
|
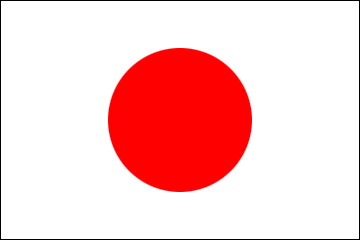 ASEAN日本政府代表部
ASEAN日本政府代表部 