代表部の活動 : 古井拓郎 参事官
令和3年3月9日
「ASEAN日本政府代表部で働いてます」→「それはなに?」参事官 古井拓郎 (2018年6月~国土交通省より出向) 以下の内容は、ASEAN日本政府代表部の立場や意見を代表するものではなく、あくまで私自身の個人的見解です。 |
|
1 プロローグ突然ですが、ASEAN(東南アジア諸国連合)日本政府代表部という組織を知っていますか? 悲しいことに、当地ジャカルタにおいて仕事以外で挨拶を交わした日本人のほぼ全員がご存じでありませんでした。例えば、当地で所属しているフットサルの新規メンバーとの初対面の挨拶はいつも同じパターンです。 私 「ASEAN日本政府代表部で働いています」 相手 「・・・。日本政府ですか?」 私 「そうです、外務省職員です」 相手 「ああっ!大使館ですか」 私 「いえいえ・・。大使館ではなく、日本政府代表部です」 相手 「・・・」 (以下、禅問答のように繰り返し。) 職場がある当地ジャカルタですらこのような状況なので、日本にいる知人・友人との会話も推して知るべし。日本語名称が分かりにくいならと、名刺に併記されている英語名「Mission of Japan to ASEAN」を伝えてみたらどうか。状況は何も変わらない、いや、更なる混乱を招く。「Mission(ミッション)」の単語に目が向いて「映画ミッション・インポッシブルみたい」だの「宣教の関係?」など、あらぬ方向に会話が進むことすらある。Missionとは「使節団・代表団」の意味だとの説明も虚しく空を切る。 そもそも、日本政府代表部がなんたるか以前に、ASEANが何か知られていないことが意外と多い。「なぜ職場はジャカルタなの?」との問いかけに、中学の社会科でASEANの本部はジャカルタに置かれていると習ったはずだけどなあ、と思わず心の中で呟く。 「ASEAN」と「日本政府代表部」という聞きなれない単語同士が組み合わさると、余計分からなくなるようだが、むべなるかな。 こうして打ちひしがれるうちに、いつしか「大使館みたいな組織です」と、やっつけ気味に説明している自分がいる。このままではいかん。そんな折、広報部から、ホームページに掲載する業務紹介の寄稿依頼がきた。渡りに船だ。どこまでお伝えできるか分からないが、やるだけやってみよう。Missionには伝道という意味もあるので。 2 ASEAN日本政府代表部の活動・業務についてASEAN日本政府代表部(以下、ASEAN代)に赴任して2年半が経過しました。新型コロナの世界的な流行により、私の勤務状況も一変しましたが、本稿では、ここでの仕事の一端をお伝えしたいと思います。まずは、プロローグで問いかけた、ASEAN代について簡単に紹介します。政府が外交などを行う海外拠点として、大使館や領事館の名前を一度は耳にしたことがあるかと思います。観光や留学ビザ取得のために、日本にある各国の大使館を訪問された方もいるのではないでしょうか。政府代表部も大使館や領事館と同じく「在外公館」の一種で、大使館が相手国に対して政府を代表しているのに対し、政府代表部は国際機関などに対して政府を代表し、特定の目的実現のため任務を遂行する組織です。我が国には、世界の中でニューヨークの国連代表部、パリのユネスコ代表部などの代表部があり、その一つであるASEAN代は、ASEANに対して日本政府を代表しています。 メディアではASEANと東南アジアが同義で語られることが多いですが、「東南アジア」は地域の名前であるのに対し、「ASEAN」は東南アジア地域の国々のうち10か国が加盟する地域協力機構または地域共同体です。地域共同体と言ってもなかなかピンとこないかも知れませんが、同じ地域共同体の部類である、町内会や自治会をイメージしてもらえれば(もちろん、役割や法的性格などは大きく異なりますが)、東南アジアの国々とASEANとの関係性について少しは分かりやすいかも知れません。 そしてASEANの各種会議や事業を担当するのが、ジャカルタに本部があるASEAN事務局です。ASEAN代では日常的にASEAN事務局やジャカルタに駐在する他国政府のASEAN代表部と仕事上のやりとりをしています。 ASEAN代での私の担当の一つが、交通分野における日本・ASEAN間の協力の推進です。ASEAN事務局、国土交通省、外務省などの関係者と一緒になって交通関連のプロジェクトの企画、調整、進捗の管理をしています。大使館と違い、二カ国間のプロジェクトは行っていません。例えば、在インドネシア日本大使館では、インドネシア国内における鉄道などのインフラ整備を支援していますが、私の場合は、基本的にASEANの全加盟国が利するようなプロジェクトです。具体例として、ASEAN加盟国の「海の管制官」の育成研修の実施や、後述の水路測量調査などがあります。 一年間の大まかなスケジュールですが、年明けから3月頃までの間に、交通分野で今後ASEANと協力したい内容を日本関係者で議論し、4月から10月頃にかけて、ASEAN事務局やASEAN各国の担当者とワーキンググループを開催して議論を重ね、最終的には11月頃に行われる、日本及びASEAN各国の大臣級が出席する「日ASEAN交通大臣会合」において、協力計画の承認を得るというプロセスが行われており、私も日本政府の一員として携わっています。 余談ですが、人気マンガのゴルゴ13に、日ASEAN交通大臣会合が主軸となるエピソードが掲載されたことがあります(第160巻「日・ASEAN会議」)。某国過激派が日ASEAN交通大臣会合を狙って爆弾テロを起こすとの情報を得た国交省の職員が、ゴルゴ13にテロの阻止を依頼し、最終的にはテロリストが仕掛けた爆弾のコードをゴルゴ13がライフルで撃ち抜き、事なきを得たというストーリーです(ちなみに、登場する国交省職員のモデルとなったのは、私の元上司で、登場人物の名前は本人とアルファベット1文字違いに設定)。幸い、私がこれまで参加した3回の交通大臣会合では、このような緊迫する事態はなく平穏に終わりました。 少し脱線しましたが、交通大臣会合で協力の行動計画が承認された後はそれに沿って、日ASEAN統合基金(略、JAIF)を活用して、関係者と一緒になって具体的なプロジェクトを企画・立案するとともに、実行段階ではその進捗を管理しています。 最後に、実施中のプロジェクトを一つ紹介します。「マラッカ・シンガポール海峡(以下、マ・シ海峡)における共同水路測量調査事業」という名前のプロジェクトです。 インドネシア、マレーシア、シンガポールの沿岸3か国の領海に挟まれているマ・シ海峡は、アジアと中東・欧州を繋ぐ重要な海上輸送路であり、年間十数万隻以上の船舶が通航する世界で最も混雑している海峡の1つです。また、海峡には浅瀬が点在することから、航行の難所として知られています。この海峡は事故のリスクが高く、一度タンカー事故が起きれば、油流出による大規模海洋汚染が発生するなど、その被害は計り知れません。このため、マ・シ海峡を通航する船舶の安全確保を目的に、海底の深さを測定して海図を作成する、水路測量調査を沿岸3か国と共同で実施しています。  以上、紙幅が尽きたので、このあたりで筆を置きますが、本稿を通じて少しでも理解を深めてもらえれば幸いです。  (向かって左側が執筆者) |
|
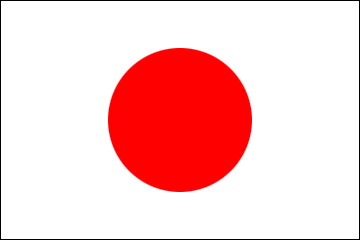 ASEAN日本政府代表部
ASEAN日本政府代表部 