代表部の活動 : 福島崇之 一等書記官
令和3年12月8日
11人12脚三段跳びの助走スタート!
|
 |
1 競技会場にたどり着くまで私は、2019年8月に法務省から出向し、現在までASEAN日本政府代表部で初代のリーガル・アタッシェ(法務担当在外公館職員)として活動しています。ここでは、これまでの経緯や業務を振り返りながら、日ASEANの法務・司法分野の協力についてご説明したいと思います。日本とASEAN各国の法務・司法分野の協力の歴史は古く、1957年、国連の日本政府との間の協定により、国連アジア極東犯罪防止研修所(UNAFEI)が設立され、現在に至るまで、ASEAN各国をはじめとする世界の開発途上国から多くの裁判官、検察官、警察官、刑務官、保護観察官等の専門家を招いて、刑事司法や犯罪防止に関する研修を行っています。1990年代には、ベトナムを皮切りに、ASEAN各国を中心とした二国間の法制度整備支援を開始し、民法等の基本法令の起草、法務・司法制度の構築、法務・司法人材の育成等の支援を25年以上にわたって取り組んできました。そのほかにも、関係機関と連携しながら、様々な分野で実務的な協力を行っています。 これらの協力は二国間が中心であり、日ASEANの協力は二国間と比較すると限定的でした。その大きな原因の1つとして、ASEAN各国の法制度が大きく異なるということが挙げられます。欧米では、裁判所の判決から生じる判例法を中心とする「英米法系」と、立法機関で制定される制定法を中心とする「大陸法系」という2つの法体系がありますが、ASEANは、その歴史的経緯から、「英米法系」に近い法制度を持つブルネイ、マレーシア、フィリピン、シンガポールと「大陸法系」に近い法制度を持つカンボジア、インドネシア、ラオス、タイ、ベトナム、その両方の要素を持つミャンマーに分かれます。これに加えて、イスラム法も導入しているブルネイ、マレーシア、インドネシアや、社会主義体制を敷くカンボジア、ラオス、ベトナムのように、宗教や政治体制も法制度に大きな影響を与えていますし、そのほかにも民族や地域の慣習等、様々な要因が絡み合って複雑なマトリクスを形成しています。 日本は、明治維新後にドイツやフランス等の「大陸法系」の法制度を導入し、第二次世界大戦後にはアメリカから「英米法系」の法制度を取り入れ、いずれも従来の法制度とうまく調和を図って定着させてきました。その経験を活かし、これまで各国の法体系や実情等に即した「オーダーメイド型」の法制度整備支援に取り組んできましたが、ASEAN各国の法制度が異なるということは、各国の課題やその解決策も当然に異なるので、二国間の支援が中心となっていくのは自然な流れでした。 しかし、2015年にASEAN共同体が発足し、ASEANは、各国が主権を維持しながらも、このような法制度の違いを乗り越えて統合を推進する道を選択しました。そのため、法務・司法分野における対ASEAN協力の文脈でも、それまで中心としてきた「二人三脚」型の協力に加え、日ASEANによる「11人12脚」型の協力も推進し、その2つをいわば「車の両輪」として連動させることにより、ASEAN各国の開発とASEANの統合を同時に実現していくことが重要となってきました。その「11人12脚」の足がかりの1つとして、リーガル・アタッシェを当代表部に派遣することとなったのです。 2 スタートラインに立つまでASEANには、柱となる政治・安全保障、経済、社会文化の3つの共同体の下に多くの分野別会合(一般に「ASEAN関連会合」と呼ばれています。)があり、各会合において日本を含む対話パートナーと対話の機会を設けています。各会合で議論した内容を具体的な協力案件に落とし込んで実行していく、というのが日ASEAN協力の基本形ですが、法務・司法関係のASEAN関連会合である「ASEAN法務大臣会議(ALAWMM)」とその下にある「ASEAN高級法務実務者会合(ASLOM)」は、日本だけでなく、そもそも対話パートナーとの交流がこれまで一切ない閉じられた存在でした。法務・司法の分野で具体的な日ASEAN協力案件を進めていくためには、まずこれらの会合との対話の機会を設けることが重要なスタートラインと考え、2018年以降、ASEAN事務局を通じて要請を続けてきました。その結果が実を結び、2018年10月にラオスで行われた両会合で対話パートナーとの協議を行っていくことで全会一致し、それまで閉ざされていた扉が初めて開かれることになりました。そして、2020年3月にミャンマーで行われるASLOMにおいて、日本との協議の場(日ASLOM協議)が設けられることとなりました。しかし、残念ながら新型コロナウイルス感染拡大の影響により会合そのものが延期となってしまいました。結局、同会合は同年10月にオンラインで開催されることになりましたが、日程の都合で会合本体のみの開催となり、日ASLOM協議の開催は見送られることとなりました。 そのような紆余曲折を経て、今年10月にオンラインで開催されたASLOMにおいて、ようやく日ASLOM協議の開催が実現しました。協議では、日ASEANの法務・司法分野の協力を更に推進するための取組について議論し、日本と共同議長を務めたマレーシアからも歓迎の意が示されました。同会合が対話パートナーと協議の場を持つのは今回が初めてであり、その最初の相手として日本を選んでくれたことを大変嬉しく、また誇りに思っています。 3 今後の跳躍に向けてこうして、日ASEANの法務・司法分野の協力関係は「11人12脚」で本格的なスタートラインを切り、助走を開始しました。タイトルで「三段跳び」と表現したのは、今後日ASEANは3つの大きなステップを迎えると考えるためです。まず1つ目のステップは2023年の日ASEAN友好協力50周年、2つ目のステップはASEAN共同体発足から向こう10年の目標を定めた「ASEAN共同体ビジョン」の最終年である2025年、そして3つめのステップは日本もASEAN各国もどちらも加盟している国連が定めた「2030アジェンダ」、つまり「持続的な開発目標(SDGs)」の最終年となる2030年です。この「三段跳び」を大きな飛躍につなげていくことが今後の日ASEAN協力にとって重要な鍵になると考えています。ASEANは、共同体の統合を進めていくに当たり、法務・司法の分野でも様々な共通課題に取り組んでいます。例えば、テロ、サイバー犯罪、薬物犯罪等を含む国境を越える犯罪への対策、汚職対策、刑事・民事共助、受刑者移送、刑務所の過剰収容対策、国際仲裁・調停等の法的紛争解決手段の推進、知的財産法を含むビジネス・投資環境の整備、越境倒産処理、商取引法の各国間の調和、法務・司法制度や人材の開発格差の是正、出入国管理や国境管理における連携等、項目を挙げていくだけでもこの紙面を埋め尽くしてしまいます。 一方で、デジタル・トランスフォーメーション(DX)等に関しては、法務・司法の分野でも成長著しいASEANで非常に先進的な取組が行われており、いわゆるリープ・フロッグ現象が起きているように思われます。このような取組から日本がASEANから学ぶということも多くあるように思います。 既に、法務省は、知的財産や汚職対策等の分野でASEANとの協力を行っていますが、日本が対話を重ねて地道にこれらのASEANの取組を支援していくことにより、この「11人12脚」による「三段跳び」を成功させ、日ASEANの法務・司法分野の協力関係の更なる飛躍を実現すべく、今後も日々の業務に取り組んでいきたいと思います。 以上 |
|
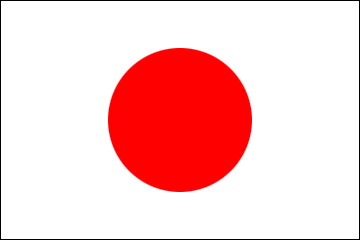 ASEAN日本政府代表部
ASEAN日本政府代表部 